会社設立・商業登記の経験が豊富な司法書士事務所
東京都千代田区で司法書士なら
ながはま司法書士事務所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町27番地1長浜ビル
JR神田駅東口徒歩3分/東京メトロ銀座線神田駅3番出口徒歩3分
定休日:土曜・日曜・祝日
新着情報

株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書・登記事項要約書・インターネット登記情報(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。この措置をとった場合、登記事項証明書等には、代表取締役等の住所は市区町村まで(東京都においては特別区まで、政令指定都市においては区まで)記載されます。
この措置は、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記(例えば、設立登記、代表取締役等の就任登記など)の申請と同時にする場合に限りすることができます。
ただし、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
代表取締役等住所非表示措置の申出(以下「申出」といいます。)には、以下の書面の添付が必要です。
<上場している株式会社の場合>
- 株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
(具体例)
株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等
<上場していない株式会社の場合>
- 本店の実在性を証する書面
(具体例)
①配達証明書と郵便物受領証
株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵
便により送付されたことを確認します。
これらに記載された商号・本店(宛先)は登記事項証明書等の記載と一致していな
ければなりません。
②登記申請を受任した司法書士等が作成する株式会社の本店所在場所における実在性を
確認した書面
現地確認、または、配達証明郵便等の郵送により、会社が実在すること確認しま
す。 - 代表取締役等の氏名及び住所を証する書面
(具体例)
①住民票の写し
②戸籍の附票
③印鑑証明書
④運転免許証や個人番号カード等の写しに、当該代表取締役等が原本と相違ない旨記載
し記名したもの - 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
(具体例)
①登記申請を受任した司法書士等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定
に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
②実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって、公証人の認証
を受けたもの
実質的支配者の氏名、住居及び生年月日を記載した書面で、申出と同時に行う登記
の申請日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限ります。
③会社設立に伴う定款認証時に公証人に申告した実質的支配者の本人特定事項について
の申告受理及び認証証明書
申出と同時に行う登記申請が株式会社の設立日の属する年度又はその翌年度に行わ
れる場合に限ります。
注)申出と同時に行う登記の申請日の属する年度又はその前年度において、法務局に実質的支配者リストの保管の申出を行っている場合は、株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面の添付は不要です。

相続人申告登記は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。
相続登記は、不動産の相続を知った日から3年以内に申請しなければなりませんが、遺産分割協議がまとまりそうにない、相続人の一部が協力しないといった事情がある場合は、相続人申告登記制度を利用することにより簡易に相続登記の申請義務を履行することができます。
具体的には、必要な戸籍謄本・除籍謄本等を添付して、自身が登記簿上の所有者の相続人であること等を不動産の相続を知った日から3年以内に不動産の管轄法務局に申し出ることで、義務を履行することができます。
ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、遺産分割協議が成立した場合や、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をしなければなりません。
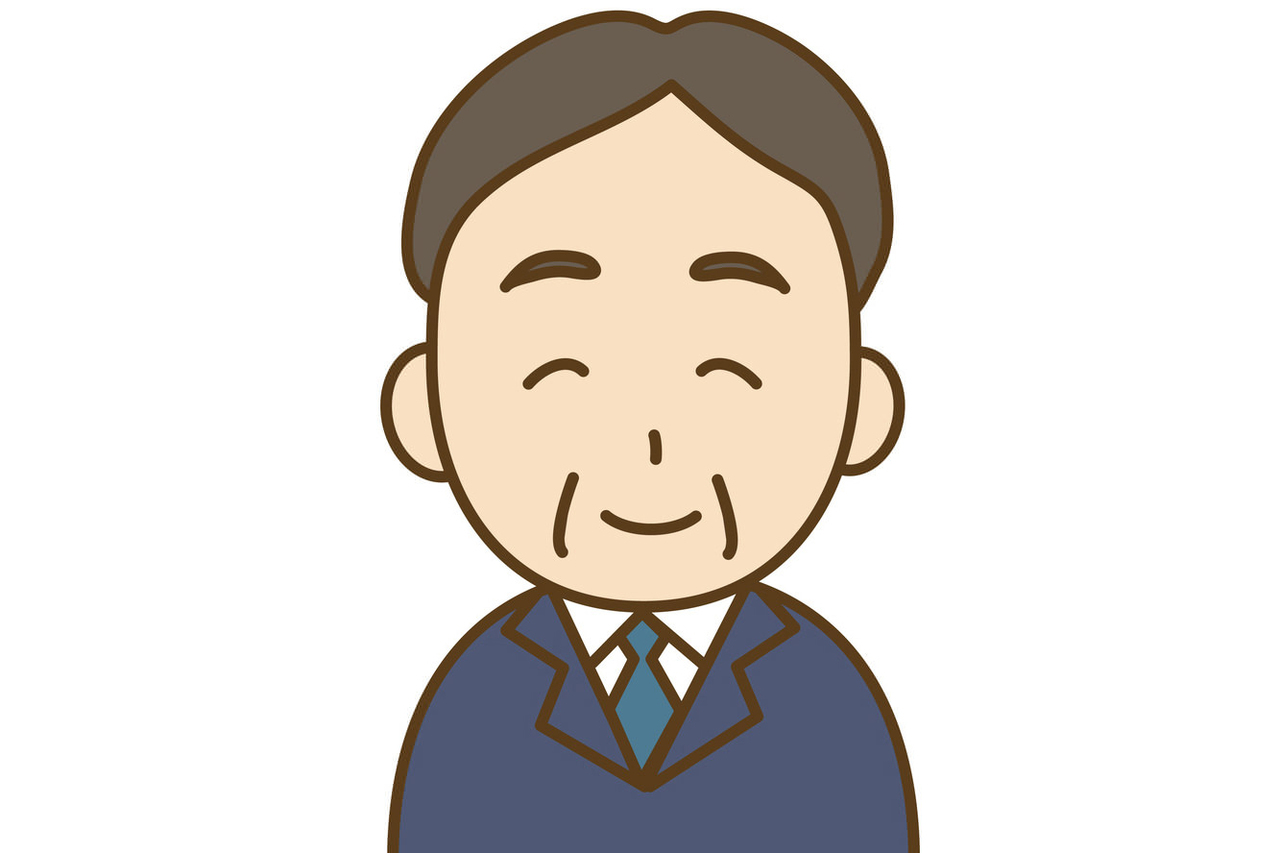
海外に在住する人及び海外に本店を置く法人が所有権を取得する登記の申請時には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の「国内連絡先事項」を法務局に提供する不動産登記法の改正がなされました。ただし、当面の間、国内連絡先となる者がないときは、その旨を記載した所有権登記名義人(所有権を取得する者・法人)の上申書を提出することで、国内連絡先となる者がない旨を法務局に提供することもできます。また、添付書類として、国内連絡先事項を証する書類、国内連絡先となる者の承諾書及び国内連絡先となる者の印鑑証明書を法務局に提供する必要があります。
この法改正は、日本に居住していない所有者(所有権登記名義人)と連絡がつきやすい環境を整えることを目的としたものであり、令和6年4月1日からスタートします。
既に所有権の登記がされている者(法人)について海外住所への移転の登記を申請する場合(海外住所から別の海外住所に移転する場合も含みます。)にも、国内連絡先事項の登記がされていないときは、上記の手続が必要となります。
国内連絡先となる者は、自然人(例えば、親族、弁護士・司法書士等の士業等)でも法人(例えば、不動産関連業者等)でも構いません。また、海外に本店を置く法人の日本国内の支店・営業所等を国内連絡先事項とすることも認められます。
具体的には、次のいずれかの事項を国内連絡先事項として申請書に記載する必要があります。
<国内連絡先となる者が自然人(個人)の場合>
・(1)氏名、(2)国内の住所(住民票上の住所)
・(1)氏名、(2)国内の営業所等(個人の事務所等)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人の場合>
・(1)名称(商号)、(2)国内の住所(本店)、(3)会社法人等番号
・(1)名称(商号)、(2)国内の営業所等(登記されている支店の他、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称、(4)会社法人等番号
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有しない外国法人の場合>
・(1)名称(商号)、(2)国内の営業所等(登記されている日本における営業所のほか、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有しない内国法人の場合>
・(1)名称、(2)住所(主たる事務所)
・(1)名称、(2)国内の営業所等(従たる事務所のほか、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者がない場合>
・国内連絡先となる者がない旨

法人(会社)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、次の(1)から(3)の「法人識別事項」を法務局に提供する不動産登記法の改正がありました。また、(2)・(3)の法人については、添付書類として、法人識別事項を証する書類(例えば、(2)の場合は設立準拠法国政府の作成に係る住所を証明する書面等、(3)の場合は当該法人の名称、住所及び設立根拠法を明らかにする公務員が職務上作成した書面)を提供しなければなりません。
この制度は、令和6年4月1日からスタートします。
法人識別事項
(1) 会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
(2) 会社法人等番号を有しない外国法人・・・設立準拠法国(※2)
(3) 会社法人等番号を有しない(1)・(2)以外の法人・・・設立根拠法(※3)
なお、名称や住所の変更の登記を申請する場合にも、法人識別事項の登記がされていないときは、上記の手続が必要となります。

土地を相続した後、「使い道がない」、「遠いので管理が難しい」などの理由により、相続した土地を手放したいというお話をよく伺います。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
この制度は、令和5年4月27日からスタートしました。
1.申請ができる人
相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。
相続や遺贈により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
土地の共有持分を相続・遺贈以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
国庫帰属制度における承認申請手続は、申請者本人が行わなければならず、法定代理人(親権者、成年後見人など)による場合を除き、第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。
ただし、司法書士は、申請書の作成を代行することができますので、制度の利用をご検討される方は是非ともご相談ください。
2.引き取ることができない土地
【申請できないケース】
①建物がある土地
②担保権(抵当権など)や使用収益権(賃借権など)が設定されている土地
③他人の利用(道路として利用するなど)が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤隣地との境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
【承認を受けることができないケース】
①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物(廃屋・放置車両など)が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物(建物の基礎・不づ位水道管など)が地下にある土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
3.審査手数料
審査手数料の金額は、土地1筆当たり14,000円となります。
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。

登記簿の付属書類(登記申請書及び添付書面)の閲覧の請求の基準を明確化、合理化する観点から、「利害関係があること」の要件が見直され、令和5年4月1日からは、登記申請人以外の第三者が閲覧の請求をする場合には、「正当な理由があること」が必要となります。
なお、ご本人が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面については、「正当な理由」の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができます。
この制度の見直しにより、登記申請書及び添付書面の閲覧を請求する際には、次の書面が必要になります。
(1) ご本人が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面の閲覧の請求をする場合
ご本人が閲覧しようとする登記申請書及び添付書面に係る登記の登記申請人であることを証明する本人確認書類(運転免許証など)
(2) 上記(1)に該当しない場合
登記申請書及び添付書面を閲覧することに「正当な理由」があることを証明する書面(訴状(案)、当事者の陳述書など)
ただし、いずれも具体的な内容が記載されたものに限られます。
令和4年10月13日、12年以上登記がされていない株式会社(休眠会社)と5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人(休眠一般法人)に対して、管轄登記所から休眠会社・休眠法人の整理作業(みなし解散)についての通知書が発送されました。
通知書の送付を受けた会社で、まだ事業を廃止していない場合には,令和4年12月13日(火)までに、その通知書を利用することによって、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
何らかの理由で、この通知書が届かなかった場合でも、休眠会社または休眠一般法人は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
令和4年12月13日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、役員変更などの必要となる登記の申請もなかった休眠会社・休眠一般法人については、令和4年12月14日(水)付で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
管轄登記所からの通知書が届かなかった場合、届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している、または本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社または休眠一般法人については,令和4年12月13日(火)までに、商号(名称)変更または本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより、解散の登記の対象とならないこととなります。
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ったり、役員変更などの登記を行った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事実は解消されませんので、 裁判所から過料が科せられる場合があります。

会社法第930条から第932条までを削除する改正会社法が令和4年9月1日に施行され、支店所在地における登記制度が廃止されます。(注)支店の登記そのものが廃止されるということではありません。
現行法では、本店所在地の管轄と異なる管轄内に支店を設置する場合は、本店所在地における支店設置登記のほかに、支店所在地を管轄する法務局にも登記申請をする必要があります。
会社法施行前は、本店の登記簿と同じ登記事項を支店の登記簿に記載する必要がありました。
しかし、本店所在地を管轄する法務局以外の法務局でも本店の登記簿を取得できるようになったこともあり、会社法施行後、支店所在地の登記事項は、「商号」「本店所在地」「支店所在地」「会社成立年月日」のみになりました。
現在では、どこの法務局でも管轄を問わず日本中の登記簿を取得できることに加え、一部の登記事項しか載らない支店登記簿の取得請求例が減少していることも影響して、支店所在地の登記簿の必要性が薄れ、支店所在地における登記を廃止することになりました。
本店所在地において支店の登記申請をしたものの、支店所在地での登記申請を失念しているという会社も散見されましたが、今後はこのような事例はなくなります。

令和4年度の税制改正により、相続登記について登録免許税が免税となるケースが拡大されました。また、登録免許税の免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。
1.相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています。
【例】A(登記名義人)死亡によりAの子Bが相続人となったが、Bが相続の手続を完了する前に死亡し、Bの妻Cが相続人となった。
登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

登記名義人
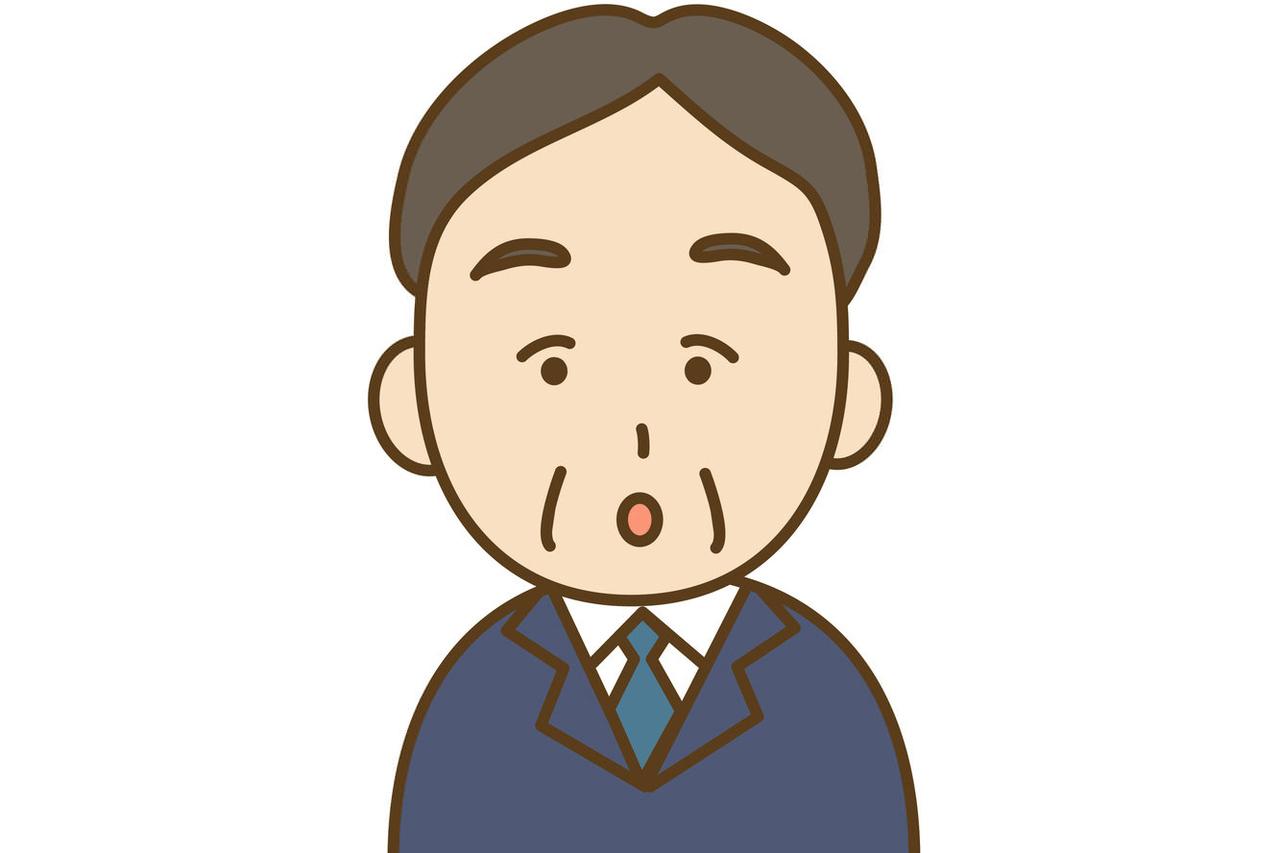
Aの相続人

Bの相続人
(注1)
BからCへの相続によるその土地の所有権の移転登記については、この免税措置の対象とはなりません。
(注2)
必ずしもCがその土地を相続している必要はなく、例えばBが生前にその土地を第三者に売却していたとしても、AからBへの相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
2.少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
個人が、平成30年11月15日から令和7年3月31日までの間に、土地について①表題部所有者の相続人による所有権の保存登記、または、②相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額(注)が100万円以下であるときは、その土地の表題部所有者の相続人による所有権の保存登記、または、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされています。
(注)市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格(固定資産評価額)がある場合は、 その価格です。固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価格になります。

相続登記の義務化を目的とする改正不動産登記法が、令和6年(2024年)4月1日に施行されることになりました。なお、住所氏名変更登記の義務化に関する改正法施行日はまだ未定です。(※ 「相続登記・住所氏名変更登記を義務化へ」をご参照ください。)

令和4年1月31日から、株式会社(特例有限会社を含む)の申出により、商業登記所が、当該株式会社が作成した「実質的支配者リスト」について、所定の添付書面により内容を確認して、その写しを発行する制度が始まります。
ここでいう「実質的支配者(BO:Beneficial Owner)」とは、株式会社の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいい、「実質的支配者リスト」とは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
この制度は、株式会社の透明性を向上させ、マネーロンダリングなどの目的による株式会社の悪用を防止するという観点から高まった金融機関等の要請を踏まえ、株式会社の実質的支配者の把握についての取組の一環として開始します。
申出の対象となる実質的支配者は次のとおりです。
① 議決権の50%超を直接・間接に保有する自然人がいる場合 ⇒ 当該自然人
② 議決権の50%超を直接・間接に保有する自然人はいないが、議決権の25%超を直接・間接
に保有する自然人がいるいる場合 ⇒ 当該自然人
この制度の手続は、株式会社の代表者又は司法書士等の代理人が株式会社を管轄する法務局に申出書・実質的支配者リスト・その他添付書類を提出し、審査完了後に認証文付きの実質的支配者リストの写しが法務局から交付されるという流れで進みます。なお、手数料は無料です。
金融機関や取引先から実質的支配者リストの提出を求められた場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

令和4年1月1日から、株式会社又は特定目的会社の定款の認証の公証人手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。
新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。1月1日前の申請のもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時を基準にします。)は、従前の一律5万円です。
令和3年10月14日、12年以上登記がされていない株式会社(休眠会社)と5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人(休眠一般法人)に対して、管轄登記所から休眠会社・休眠法人の整理作業(みなし解散)についての通知書が発送されました。
通知書の送付を受けた会社で、まだ事業を廃止していない場合には,令和3年12月14日(火)までに、その通知書を利用することによって、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
何らかの理由で、この通知書が届かなかった場合でも、休眠会社または休眠一般法人は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
令和3年12月14日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、役員変更などの必要となる登記の申請もなかった休眠会社・休眠一般法人については、令和3年12月15日(水)付で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
管轄登記所からの通知書が届かなかった場合、届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している、または本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社または休眠一般法人については,令和3年12月14日(火)までに、商号(名称)変更または本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより、解散の登記の対象とならないこととなります。
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ったり、役員変更などの登記を行った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事実は解消されませんので、 裁判所から過料が科せられる場合があります。

令和3年度の税制改正により、次の2つの登録免許税の免税措置について、その適用対象に一定の所有権の保存登記が追加されるとともに、これらの登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和4年3月31日まで1年延長されました。(※令和4年度の税制改正により、適用期限と適用対象が変更されました。「相続登記の登録免許税の免税対象が拡大」をご参照ください。)
1.相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています。
【例】A(登記名義人)死亡によりAの子Bが相続人となったが、Bが相続の手続を完了する前に死亡し、Bの妻Cが相続人となった。
登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。

登記名義人
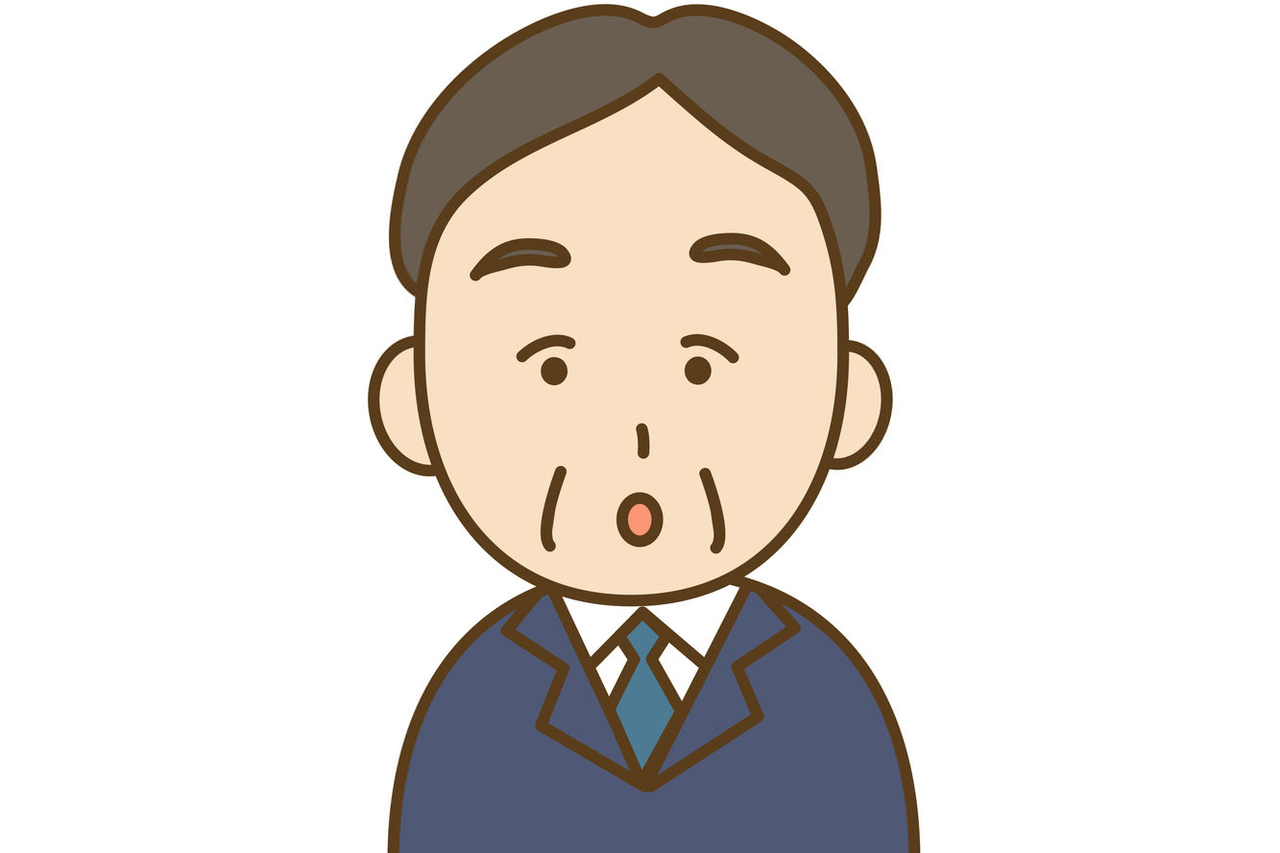
Aの相続人

Bの相続人
(注1)
BからCへの相続によるその土地の所有権の移転登記については、この免税措置の対象とはなりません。
(注2)
必ずしもCがその土地を相続している必要はなく、例えばBが生前にその土地を第三者に売却していたとしても、AからBへの相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
2.少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
個人が、平成30年11月15日から令和4年3月31日までの間に、土地について①表題部所有者の相続人による所有権の保存登記、または、②相続による所有権の移転登記を受ける場合において、㋑その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地(注1)であり、かつ、㋺その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額(注2)が10万円以下であるときは、その土地の表題部所有者の相続人による所有権の保存登記、または、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされています。
(注1)
市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象とされ、法務大臣の告示で定められています。法務大臣が指定する土地については、法務局・地方法務局のホームページに掲載されています。
(注2)
市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格(固定資産評価額)がある場合は、その価格です。固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価格になります。

令和3年2⽉15⽇に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されたことにより、登記所に印鑑(会社実印・法人実印)の提出義務を定めていた従前の商業登記法第20条が削除されました。
しかし、以下の場合は、従前どおり会社実印や法人実印の提出が必要です。
・本人による申請、かつ、書面申請の場合
・代理人(司法書士等)による申請、かつ、登記委任状を書面で提出する場合
言い換えると、会社または法人が商業・法人登記をオンライン申請する場合と、代理人(司法書士等)に電子署名を付した登記委任状を交付する場合は、会社実印・法人実印登録していなくてもよいということになります。
会社実印・法人実印を登録しない場合には、一部の添付書類に市区町村に登録した印鑑(個人の実印)の押印+印鑑証明書添付が要求されることがあります。ただし、添付情報(PDFを利用して電子化された添付書類)には、常に作成者が電子署名をし、電子証明書を記録しなければなりません。

令和3年2⽉10⽇、法制審議会は、相続の登記や住所・⽒名の変更の登記の義務付けなどを内容とする、⺠法・不動産登記法(所有者不明⼟地関係)の改正等に関する要綱を採択しました。改正法律案は、近く通常国会に上程される予定です。
改正法立案によると、不動産の所有権の登記名義人に相続が発生し,かつ,それによって当該登記名義人から当該不動産を取得したことを知った日から,3年以内に相続の登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのに相続の登記の申請を怠ったときは,10 万円以下の過料に処されます。
また、同案によると、転居,婚姻,商号変更又は本店移転等によって不動産の登記名義人の氏名,名称又は住所が変更された日から,2年以内に当該変更の登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのに登記の申請を怠ったときは,5万円以下の過料に処されます。






